

[公開日] 2023 年 8 月 22 日午前 6 時 17 分 (AEST)
[著作者] Oscar Davis
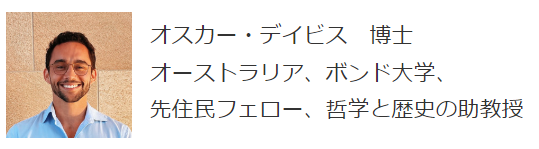
私たちはどうすれば良い、充実した人生を送ることができるのでしょうか?
アリストテレスは、『ニコマコス倫理学』(Nicomachean Ethics) の中でこの問題を初めて取り上げました。おそらく、西洋の知的歴史の中でこの問題を独立した問題として注目したのはおそらく初めてです。
彼は、私たちがどのように生きるべきかという問いに対する目的論的な答えを定式化しました。 言い換えれば、アリストテレスは、種としての私たちの目標や究極の目的(テロス)についての検討に基づいた答えを提案しました。
私たちの目的は、私たちの本質、つまり人間であることが何を意味するかの基本的な特徴を研究することによって明らかにできる、と彼は主張しました。
究極の目的と本質
「あらゆるスキルとあらゆる探求、そして同様にあらゆる行動と合理的な選択は、何らかの善 (good) を目的としていると考えられています。」 アリストテレスはこう述べています。「善とは、すべてが目指すものとして適切に表現されているのです。」
何が善であるかを理解するには、したがって善を達成するために何をしなければならないかを理解するには、まず自分がどのようなものであるかを理解する必要があります。 これにより、実際にどのような機能が良いのか悪いのかを判断できるようになります。
アリストテレスにとって、これは一般的に当てはまる真実です。 たとえば、ナイフを考えてみましょう。 何が適切な機能を構成するのかを判断するには、まずナイフが何であるかを理解する必要があります。 ナイフの本質は切ることです。 それがその目的です。 したがって、鈍いナイフは悪いナイフであると主張できます。切れ味が悪い場合は、重要な意味でその機能を適切に果たせていないことになります。 これが本質と機能の関係であり、その機能を果たすことが問題の物体にとってある種の善性を伴うことです。
もちろん、ナイフやハンマーの機能を決定することは、ホモ・サピエンスの機能を決定するよりもはるかに簡単であり、したがって、充実した素晴らしい人生とはどのようなものであるかを決定することは、種としての私たちにも関係するかもしれません。
アリストテレスは、植物にもそれが可能であるため、私たちの機能は成長、栄養、生殖以上のものでなければならないと主張しています。 人間以外の動物にもそれが可能であるため、私たちの機能は知覚以上のものでなければなりません。 したがって、彼は、人間の本質、つまり人間をユニークにしているものは、人間が推論する能力を持っていることであると提案しています。
したがって、善良で繁栄した人間の生活には、「理性のあるその部分の、ある種の実際的な生活」が含まれるのです。 これがアリストテレスの倫理学の出発点です。
私たちは、適切に論理的に考え、実践的な知恵を養うことを学ばなければなりません。また、この論理を自分の決定や判断に適用する際に、美徳の過剰と不足の間の適切なバランスを見つけることを学ばなければなりません。
「理性に従った高潔な活動」の生活、つまり私たちを定義するものへの深い理解と感謝から生まれる機能を開花させ、果たす生活によってのみ、私たちはユーダイモニア (eudaimonia) 、つまり最高の人間性を達成することができます。

実存は本質に先立つ
アリストテレスの答えは非常に影響力があり、何千年にもわたって西洋の価値観の発展を形作りました。 トマス アクィナス (Thomas Aquinas) などの哲学者や神学者のおかげで、彼の永続的な影響は中世からルネサンス、そして啓蒙主義にまでたどることができます。
啓蒙時代には、アリストテレスの著作を含む支配的な哲学的および宗教的伝統が、新しい西洋の思想原則に照らして再検討されました。
18 世紀に始まる啓蒙時代には近代科学が誕生し、それに伴い、文字通り「誰の言葉も信じない」という言葉のヌリウス原則 (nullius in verba) が採用され、これが王立協会 (Royal Society) のモットーになりました。 それに応じて、現実の性質、ひいては私たちがどのように人生を生きるべきかを理解するための世俗的なアプローチが急増しました。
これらの世俗哲学の中で最も影響力のあるものの 1 つは実存主義 (existentialism) でした。 20世紀、実存主義の中心人物であるジャン=ポール・サルトル (Jean-Paul Sartre) は、神学に頼ることなく人生の意味を考えることに挑戦しました。 サルトルは、アリストテレスとアリストテレスの足跡をたどった人々はすべてを裏から表に導いたと主張しました。
photo: Jean Paul Sartre (1967) Wikimedia Commons, CC BY-SA
実存主義者は、私たちが一見終わりのない選択をしながら人生を送っていると見ています。 私たちは何を着るか、何を言うか、どのようなキャリアをたどるか、何を信じるかを選択します。 これらすべての選択が私たちを形成します。 サルトルはこの原理を「実存は本質に先立つ “existence precedes essence” 」という式にまとめました。

実存主義者は、私たちが自分自身を創造するのは完全に自由であり、したがって、私たちが採用することを選択したアイデンティティに対して完全に責任があることを私たちに教えます。 サルトルは、1946年のエッセイ『実存主義はヒューマニズム (Existentialism is a Humanism) 』の中で、「実存主義の第一の効果は、すべての人がありのままの自分を所有し、自分の存在に対する全責任を真正面から自分の肩に負わせることである。」と書きました。
実存主義者たちは、真の人生を送るために重要なのは、私たちが何よりも自由を望んでいることを認識することだと言うでしょう。 彼らは、私たちが根本的に自由であるという事実を決して否定すべきではないと主張します。 しかし、彼らはまた、私たちが何になれるか、何ができるかについて非常に多くの選択肢があるため、それが苦しみの原因であることも認めています。 この苦悩は私たちの深い責任の実感です。
実存主義者たちは、ある重要な現象に光を当てています。それは、私たちは皆、ある時点で、そしてある程度、逃れられない自由の苦悩から逃れるために「外部の状況に束縛されている」と自分自身を思い込んでいるということです。 私たちがあらかじめ定義された本質を持っていると信じることは、そのような外部状況の 1 つです。
しかし実存主義者たちは、他にも心理学的に明らかなさまざまな例を提供しています。 サルトルは、パリのカフェでウェイターを観察した物語を語ります。 彼は、ウェイターの動きが少し正確すぎ、少し速すぎ、そして少し印象づけることに熱心すぎるように見えることに気づきました。 サルトルは、ウェイターがウェイターであることを誇張しているのは演技であり、ウェイターは自分をウェイターであると偽っていると信じています。
そうすることで、ウェイターは本来の自己を否定するのだとサルトルは主張します。 彼は代わりに、自由で自律的な存在以外の何かのアイデンティティを引き受けることを選択しました。 彼の行為は、彼が自分の自由、そして最終的には自分自身の人間性を否定していることを明らかにしています。 サルトルはこの状態を「不誠実 (bad faith) 」と呼んでいます。
本当の自分の人生
Picture: Michel de Montaigne – artist unknown c.1570. Wikimedia Commons
アリストテレスのエウダイモニアの概念に反して、実存主義者は真に自分として行動することが最高の善であると考えています。 これは、私たちが自由であることを否定するような行動は決してしないことを意味します。 私たちが選択をするとき、その選択は完全に私たちのものでなければなりません。 私たちには本質がありません。 私たちは自分たちで作るものにほかなりません。

ある日、サルトルのもとを生徒が訪ねてきて、フランス軍に加わって兄の仇を討つべきか、それとも家にいて母親を支えるべきかについてアドバイスを求めました。 サルトルは、道徳哲学の歴史はこの状況では何の役にも立たないと信じていました。 「あなたには自由があるのですから、選んでください」と彼は生徒に答えました。「つまり、発明してください」。 生徒ができる唯一の選択は、まさに彼自身のものでした。
私たちは皆、自分の人生の意味や目的について感情や疑問を抱いていますが、それはアリストテレス派、実存主義者、またはその他の道徳的伝統のいずれかの側につくというほど単純ではありません。 ミシェル・ド・モンテーニュは、エッセイ「哲学を学ぶことは死ぬことを学ぶことである That to Study Philosophy is to Learn to Die」(1580) の中で、おそらく理想的な妥協点を見つけています。 彼は「死の計画は自由の計画である “the premeditation of death is the premeditation of liberty” 」そして「死ぬことを学んだ者は奴隷であることが何であるかを忘れている “he who has learnt to die has forgot what it is to be a slave” 」と主張します。
モンテーニュは彼の典型的な冗談のスタイルでこう締めくくりました。「私は、死神にキャベツの植え付けに連れて行ってほしいです。でも彼のことをよく考えないで、ましてや私の菜園はまだ完成していないのに。“I want death to take me planting cabbages, but without any careful thought of him, and much less of my garden’s not being finished.”」(注1)
おそらくアリストテレスと実存主義者は、目的、自由、真正性、死すべき運命といったこれらの事柄について考えることによってこそ、自分自身を決して理解できないという沈黙を克服できるということに同意するかもしれません。 この意味で、哲学を学ぶことは生き方を学ぶことです。

この記事は、クリエイティブコモンズライセンス(CCL)の下で The Conversation と各著作者からの承認に基づき再発行されています。日本語訳は archive4ones(Koichi Ikenoue) の文責で行われています。オリジナルの記事を読めます。original article.
[編集者注] 注1:原典 (英訳) では、以下のセンテンスです。このほうが理解し易いと思います。
I would always have a man to be doing, and, as much as in him lies, to extend and spin out the offices of life; and then let death take me planting my cabbages, indifferent to him, and still less of my garden’s not being finished. I saw one die, who, at his last gasp, complained of nothing so much as that destiny was about to cut the thread of a chronicle he was then compiling, when he was gone no farther than the fifteenth or sixteenth of our kings:
私には常に、自分の日常の仕事を拡張したり新分野へ進出するために、求められる使用人が必要だろう。そして、私は、死神にキャベツの植え付けに連れて行ってほしいです。でも彼のことをよく考えないで、ましてや私の菜園はまだ完成していないのに。私が見たある人は、最後のあえぎの際に、当時編纂していた年代記の糸が運命に切られそうになったこと以外は何も不平を言わず、私たちの王の15代か16代を過ぎたところで亡くなりました。



